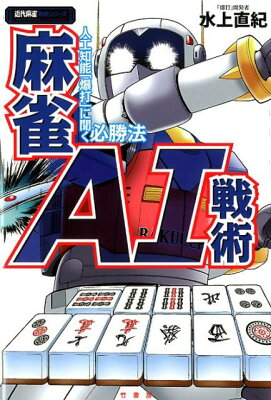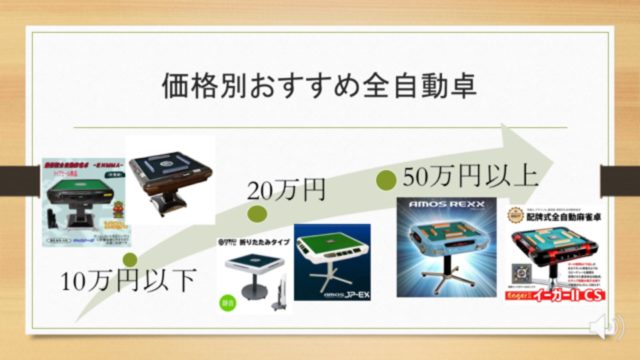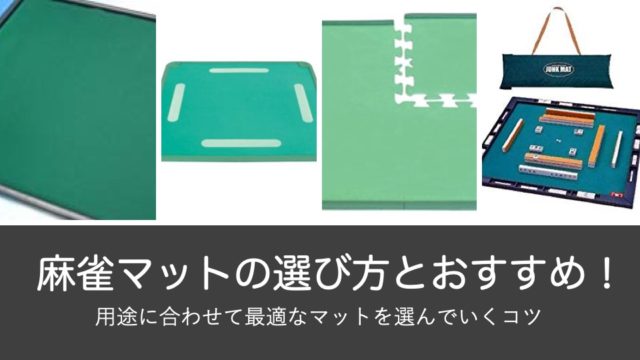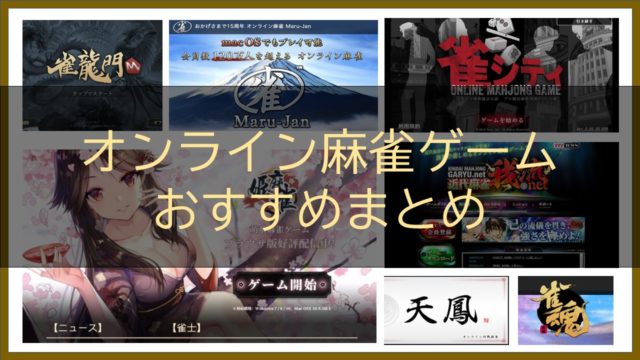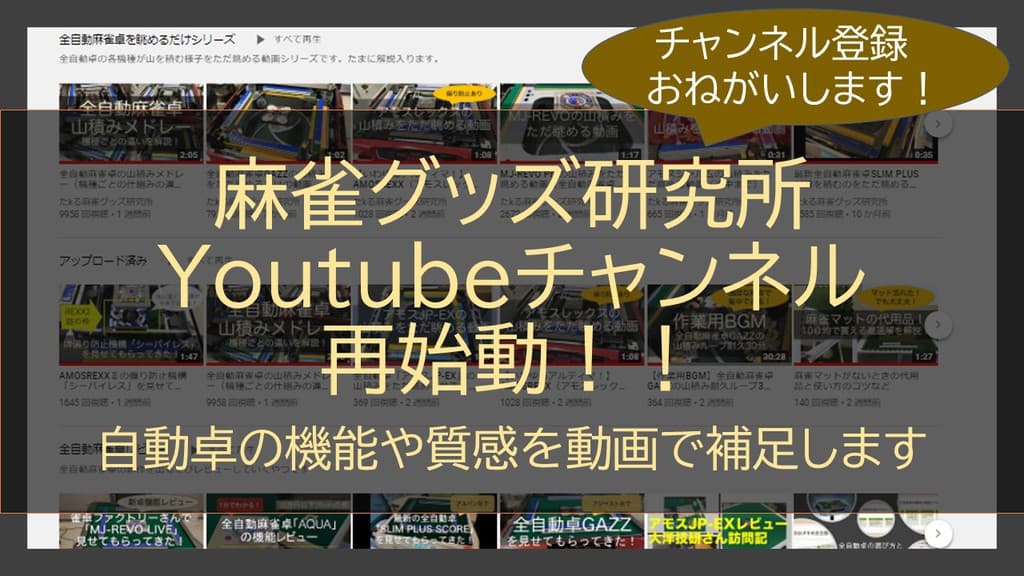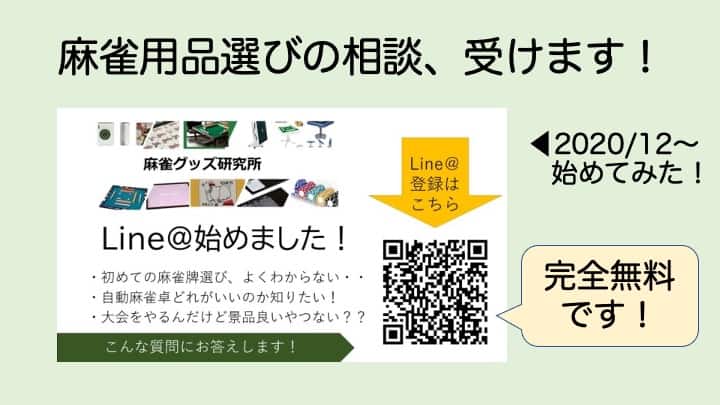麻雀好きな大学生ともなると、卒論のテーマに麻雀を選びたいこともあるかと思います。
そこで今日は、麻雀で卒論を書くための方法として、テーマ選び、調査、執筆の各ステップのコツを解説します。
目次
麻雀で卒論を書くための流れの全体像
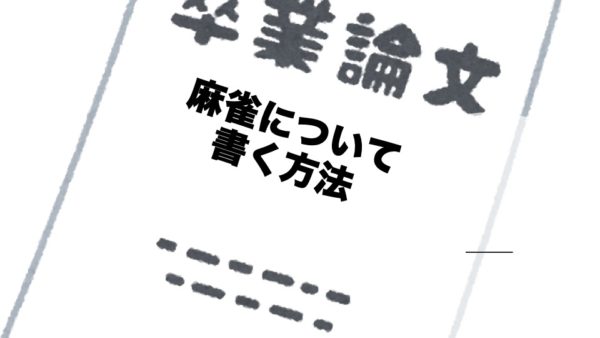
まずは卒論を書くための流れの全体像について簡単に紹介します。
卒論を書くためには大きく以下の3つのステップが必要となります。
・テーマ選び
・調査
・執筆
ざっくりしたイメージとしては、卒論の提出が1月末だとして、テーマ選びが9月くらいまでに終われば、まあ最悪なんとかなります。
調査は内容にもよりますが、文系なら2〜3ヶ月あればとりあえず形にはなって、執筆は最悪2週間くらいあれば50ページくらいは書けるはず。
では以下ではそれぞれのステップについて見ていきましょう。
麻雀で卒論を書くテーマ選び!AIや文化としての麻雀は熱い
まずはテーマ選びについて。
本格的なテーマ選びをする前に、ざっくりとしたイメージを掴む上でジャンル分けが必要となります。
麻雀が論文として認められやすい分野としては、(もちろん教授の意向次第みたいなのはありますが)以下のテーマかなと思います。
・麻雀AIのアルゴリズム
・麻雀の歴史
・文化としての麻雀
ギャンブルとか趣味としての麻雀はあまり認められない傾向にあります。
それぞれ簡単に解説します。
麻雀AIのアルゴリズム
まず一つ目としてもしあなたが情報系でビッグデータ系、AI系の研究室にいるなら話は早い。
麻雀におけるAIという分野は今最も熱い分野の一つだからです。
麻雀は将棋や囲碁に比べて不確定要素が多いのでAIは難しい、というのが一昔前の流れでしたが、最近では天鳳九段の爆打を皮切りに、Naga、SuperPhenixなどの高段位麻雀AIが多数出ています。
しかも天鳳十段のSuperPhenixはマイクロソフト系列の会社の作成とのことで、大手企業も開発に乗り出しており、需要がある分野です。
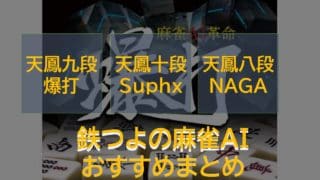
王道の麻雀の歴史
続いては文系でも使えるテーマとして王道な麻雀の歴史です。
麻雀の歴史は実はそんなに深くなくて、現代の麻雀の原型となったのは100年くらい前にアメリカから持ち込まれたリーチ麻雀だと言われています。
で、ただその歴史がイマイチ定まっていなくて、明治・大正の文豪とかの文章にちょっと出てくるからこの辺だろう!みたいなくらいにとどまっています。
なので研究テーマとしては結構意味があって、麻雀の輸入とか変遷をまとめれば成果が出そうです。
一方、麻雀の元になったゲームとしての歴史だとかなり長くて、以下の本にも詳しく書かれていますが、諸説があり、テーマとしては奥行きがあります。
ただそこまで深追いしなくとも、世界中で麻雀ぽいゲームみたいなのはたくさんあるので、それらの違いをまとめていくのも一つのテーマとして成立しそう。

文化としての麻雀!認知症対策、地域活性化など
3つ目のジャンルとしては、現在の文化としての麻雀です。
例えば、健康麻雀として老後のつながりを生み出すためのツールとしての麻雀であったり、認知症予防の効果を期待できる、など、社会問題と絡めて麻雀の有用性を説明できる分野であれば、研究テーマとしては有用となります。
具体的には地域活性化と認知症対策、インバウンド(海外にも日本式麻雀のファンは多い)などが良さそう。

麻雀卒論調査編!客観的な視点が必要
では続いては、麻雀卒論における調査のやり方についてです。
テーマが決まったらすぐ執筆!と行きたくなるところですが、研究においてはフィールドワークというか、理論の裏付けを取っていく必要があります。
で、そのやり方としては、研究テーマにもよるかと思うんですが、AIのアルゴリズムなどであれば、実際に作っての検証とかが必要だし、文系の研究テーマであれば、地域コミュニティへのインタビューなどが必要。
注意したいのは、麻雀が好きなので麻雀の流れについて書きます!とか戦術書きます!では通りにくいということ。
あくまで一般に意味のある内容が求められます。
ただいずれにしても序論の部分はもう書いてOKです。(ここを先に書いておかないと何を調べればいいのかが明確にならない上、後で時間がなくなった時にきつい)
麻雀卒論執筆編!1ヶ月くらいとっておくと安心
最後は執筆編です。
しっかりテーマが明確になっていて、そのテーマを裏付けるためのデータも揃っていれば、卒論をまとめること自体はそんなに難しくはないです。
多分二週間もあれば、50ページくらいの論文でも仕上げられるはず。
ただ、実際にはそんなにうまくはいかず、「しまった!この理論で行くならこのデータも必要だったか!」とかそういうのが急遽出てくることが多いので、余裕を持って1ヶ月くらいを執筆期間でとっておくのがおすすめ。
書き方としては、「である」調で事実を淡々とまとめていけばOKです。
失敗しがちな卒論の進め方
最後に失敗しがちな卒論の書き方として、悪い例を紹介します。
悪い例としては以下のようなものがあります。
・秋くらいまでサボり続けて「麻雀で書きます!」という
⇨いや急に来て麻雀って・・・となりがち。
・麻雀をテーマに!といって雀荘にこもる
⇨麻雀打ちたいだけでは?と思われがち
・独自の麻雀理論を提唱しだす
⇨客観性なくね?その研究意味あんの?となりがち
まあ、説明は不要かなと思うので、これで終わります。
ポイントは教授の許可はちゃんと取ろう!ということです。
ちなみに、戦術系の論文もあるにはあって、以下の論文では、麻雀における打牌選択のロジックを決定木でモデル化したという内容で執筆されていたりします。
麻雀論文の先行研究一覧【卒論・修論の下準備】
最後に巻末として麻雀に関する論文をいくつか紹介(というか列挙)します。
自分のテーマを探す際の参考にお使いください。
・・・適当にピックアップしただけでもたくさんありました。意外と麻雀で卒論ってかけるもんなんですね!
終わりに
ここまで簡単にではありますが、麻雀で卒論を書くための方法とコツについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
麻雀はうまいこと使えば独自性が出せていい感じになる分野です。
麻雀が得意な人はぜひ効果的な形で使っていきましょう。
就活とかでも使えます。
ではまた。良い麻雀ライフを!