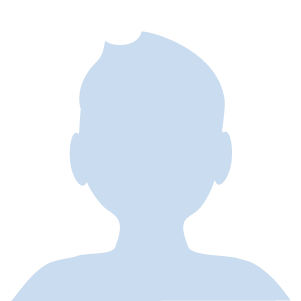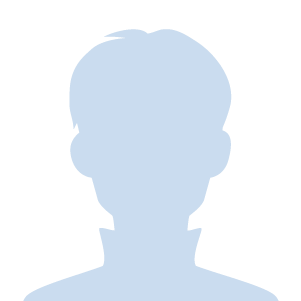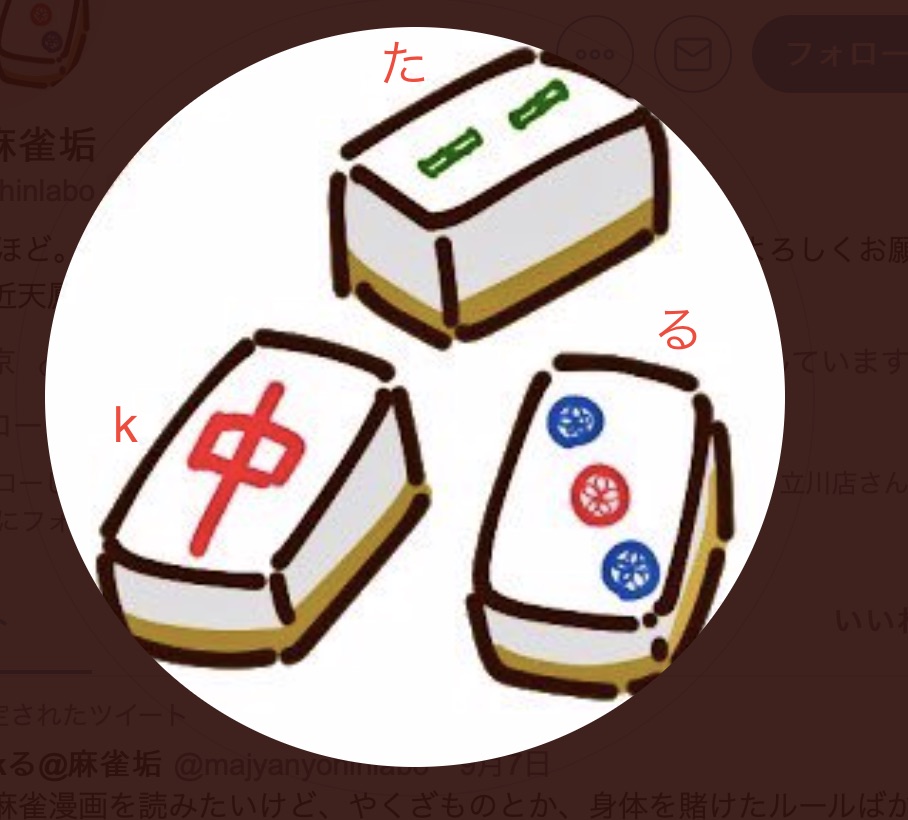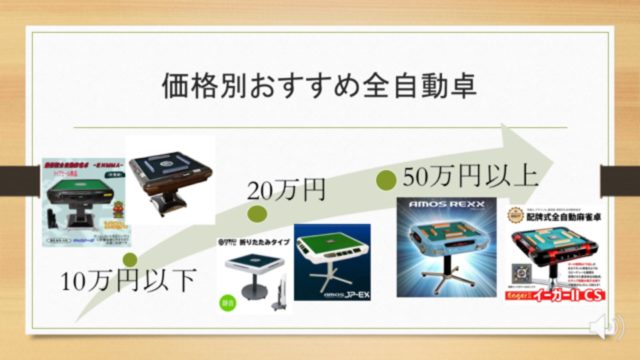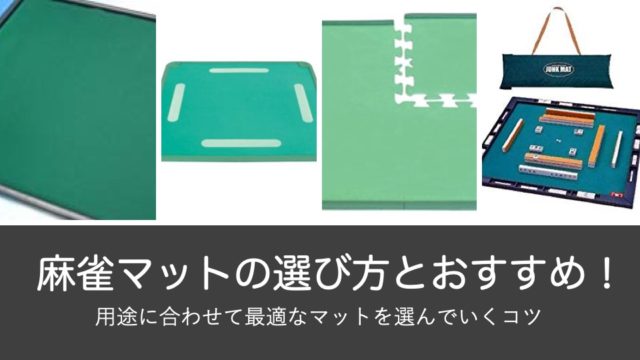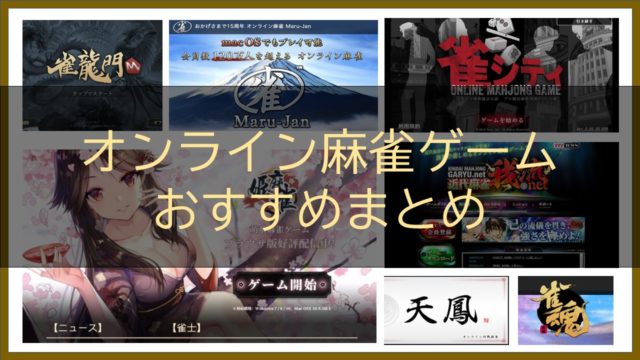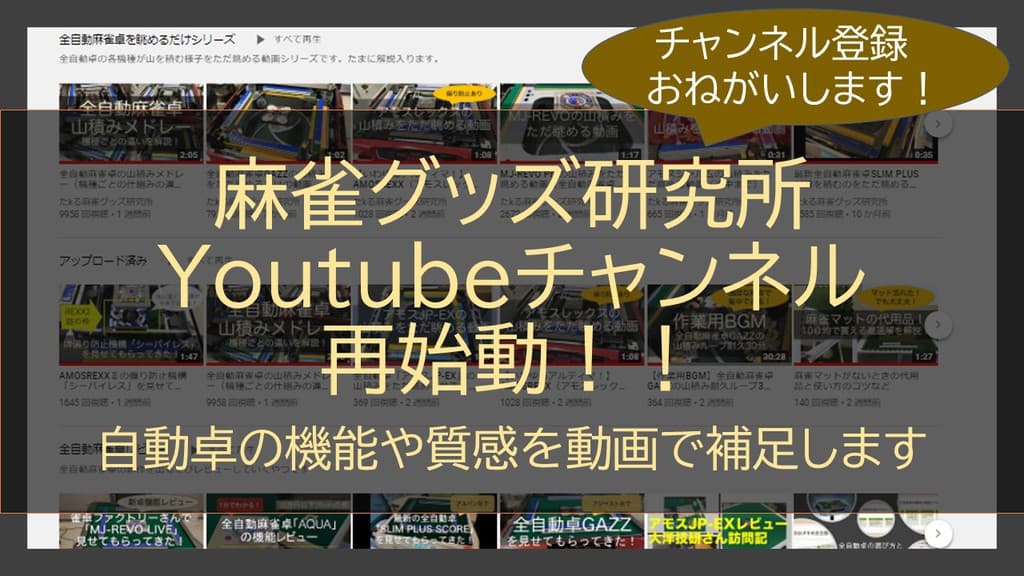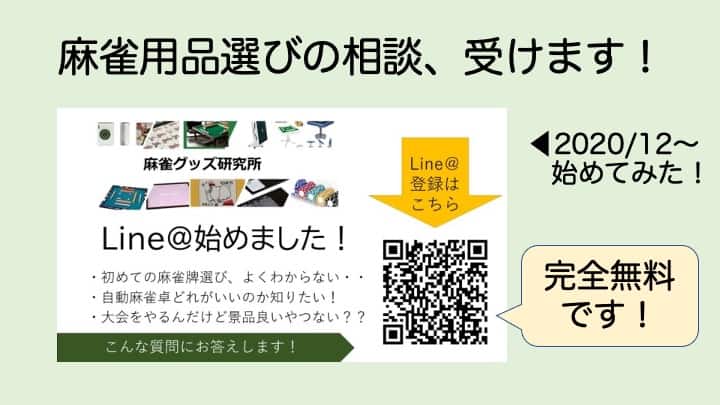修学旅行や合宿などで移動時間や宿泊地で遊ばれるゲームとしてはトランプとUNOが一般的です。
トランプはどのゲームをやるかを選ぶ必要があり、枚数も54枚の縛りがあるため、大人数の場合にはUNOが選ばれる場合が多いです。
そして、このたび、そのUNOを麻雀打ち同士が遊ぶとかなりめんどくさいゲームになるということが判明しました。
今日は麻雀打ち同士がUNOをするとなぜ、めんどくさいのかについて体験を語ります。
簡単に言うと、みんなでワイワイ楽しむはずのUNOが、高度な情報戦となり疲れます(笑)。
目次
まずはUNOの正式ルールをおさらい
ルールにうるさいのが麻雀打ちの特徴(偏見)ですが、実際、UNOはローカルルールが多いです。
なのでまずは一度UNOの正式ルールをおさらいしましょう。
UNOは和了は一人だけ
まず大原則として、UNOは一人勝ちのルールで、一人和了したらその場でゲーム終了です。
和了できなかった残りの人は、残った手札に応じてペナルティポイントが減点されていきます。
これを全5ラウンド行い、最終的に得点が高い順から1位、2位……と順位を決定するのがUNOのルールです。
このルールは自分も大学に入ったくらいに初めて知って、それまでは、ババ抜きのようなラスを決めるルールだと思っていました。
麻雀で言えば、3人が和了するまでゲームが終わらないようなイメージ。
麻雀で考えるとサドンデス感半端ないですね(笑)
ちなみに減点のルールは、
- 数字カードは額面通り0~9ポイント
- スキップ、リバース、ドロー2は各20ポイント
- ワイルド、ワイルド・ドロー4は各50ポイント
として計算します。
ドロー4を4枚とか持った状態で和了されると、役満を食らったような感じになります。
使用するカード
UNO公式ルールによると、使用するカード枚数についても決まりがあります。
赤、青、黄、緑の4色の数字カード(0のみ各1枚、1~9は各2枚)とリバース、スキップ、ドロー2の3種類のアクションカード(各2枚)、そして色指定のないワイルド、ワイルド・ドロー4の2種類のアクションカード(各4枚)の合計108枚を1セットとする。
108枚1セットなので、トランプよりは2倍程度多いですが、麻雀よりは少し少ないですね。
サンマくらいの枚数です。(サンマは108牌)
このくらいの枚数なら麻雀打ちは残り枚数をカウンティングしてくる人間とそうでない人間に分かれます。
だから麻雀打ちがUNOを打つと、記憶量の差で色々起きたりしてめんどくさいです。
麻雀打ちでUNOを打ってみたら定石にうるさかった話
UNOの人数は2~10人ですが、最適は4~6人とされています。
実際、自分が打った時は5人でプレイしました。
手札を7枚ずつ配り、ゲームをスタートします。
初めのうちは静かに進んでいきましたが、手札枚数が減ってくると、麻雀打ちらしさができてきます。
いくつか気づきをまとめました。
単騎待ちはアガレない
まず、麻雀打ち同士でUNOをやって思ったのが、単騎待ちはまず和了できないということ。
普通に枚数を減らしていって、2枚の状態から1枚を出してUNOを宣言する。
そして次順に、偶然同じ色が回ってきてアガリ、というのはUNOの王道パターンですが、麻雀打ち同士のUNOでは、残り一枚ともなれば、色はほぼ読まれているし、場合によっては数字もかなり絞り込まれます。
とか、そういったアグレッシブな読みを編み出す奴も出てきます。
なので、麻雀打ち同士のUNOでは、如何にカードを重ねて、UNO(立直)をかけずにダマで和了するかが重要です。
ドロー2系の使い方で勝敗が分かれる
使いどころが難しいのがドロー2系です。
持っていると、誰かにダマで和了されたときにダメージを受けますが、持っていないと、ドロー2の連鎖が発生したときなどに大量ドローの憂き目にあうこともあり、判断がむずかしいカードです。
麻雀打ち(特に天鳳プレイヤー)が多く集まっている場合、トップ目が大量ドローをした場合などは結託して早上がりに走る流れが出来上がることもあるので、トップ目の場合などは、ドロー2抱え落ちのリスクを抱えてでも、安全牌としてキープしておく場面は多々あります。
ただ、あまりに定石通りだと、
とか、なんかアクロバティックな読みをしてくる奴も出てきたりして、面白いです。
ともあれ、全員の利害が一致する場を以下に作るか(あるいは作らせないか)も勝負のカギです。
オーラスは上位グループが早和了を狙うがアガっても逆転できないことも
5ラウンド目、麻雀で言ういわゆるオーラスでは、僅差のトップグループはとにかく早和了を狙っていきます。
ただ、和了できれば勝ちかといえばそうでもなくて、
「1点差の2着目がアガったものの、1着目の残り手札が0のみだった」
みたいなドラマが起こるのがUNOの面白いところです。
逆に、オーラスで断ラスとかだとほぼ逆転は不可能になるので、以下にトップグループに着けておくかがUNOにおいては麻雀以上に重要です。
UNOにおけるイカサマに関して
ちなみにUNOにおいてイカサマを警戒する必要性はちょっとあります。
麻雀において警戒する内容と大体同じですが、具体的には以下の3つを覚えましょう。
- 空気が読めるもの同士の結託
- エレベーター
- カードの積み込み
まあ、一つ目はイカサマというほどではないですが、Win-Winの関係の両者が結託して上がりに向かうというパターンですね。
2つ目はカードを見えないところで交換するイカサマ。これはもしやられたらひとたまりもないので注意しましょう。
3つ目は露骨に積み込むやり方の他に、カードの偏りを予測してシャッフルで混ざりきらない読みのカウンティングがあり得ます。
なので、前局でリバースが続いていた場合、次の局では山にリバースが固まる可能性などがあります。
対策としては山をいくつかに分けておくなどがおすすめ。
終わりに!5人以上の麻雀合宿ではUNOをプレイするのもおすすめ!
自分たちは、麻雀合宿の前哨戦として行きのバスの中でUNOをして、本気でプレイしすぎて5人中3人が酔うという悲惨な結果となりました。
麻雀打ち同士でUNOを打つ場合は、かなり熾烈な情報戦となることが予想されるので、コンディションに気を付けてプレイしましょう。
ちなみにバス内とかで麻雀を打ちたい人にはカード麻雀がオススメです。
(⇒オシャレなカード麻雀でいつでもどこでも対局しよう)